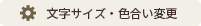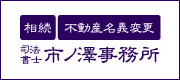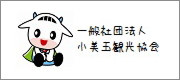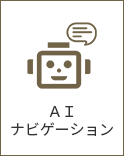文化財一覧(小川エリア2)

天聖寺は、宝永4年(1707年)水戸の祇園寺三世「蘭山」がこの小川の地に隠棲し、開基となった。天聖寺は蘭山没後、慈眼・雪庵・彗明等歴代の和尚によって守られてきたが、幕末の元治甲子の乱で荒廃し、廃寺となったが、この墓碑に往時の繁栄が偲ばれる。(史跡)
本間玄琢一族の墓

潮来から小川に移り住んだ本間家は、文化元年(1804年)時の当主本間玄琢が、現在の小川小学校の地に医学研究所を開設し、水戸藩主徳川治保より「稽医館」の名を賜った。「稽医館」は当時では大変新しい種痘の研究等が行われ、高度な医学研究所であった。墓は天聖寺の墓地内にあり四代道意・五代玄琢・六代玄有の墓と、芭蕉の句が刻まれた句碑等がある。(史跡)
天妃尊

天聖寺境内に所在し、古くは海上安全の神様として奉られていた。中国の僧心越禅師が日本に渡るとき、海上安全の神様として持参したものを徳川光圀公(義公)の命により三体複製し、その内の一体を天聖寺に奉ったと伝えられている。(彫刻)
石造地蔵菩薩(日限り地蔵)

下馬場に所在し、地蔵塚古墳の墳頂に奉られている。高さ1.2mの石の地蔵尊で、願い事を希望する日時にかなえてくるので、日限り地蔵と言われている。毎月旧暦の24日が縁日である。(彫刻)
木造地蔵菩薩(赤身地蔵)

本田町に所在し、小川市街を一望できる高台に奉られている。高さ46cmの檜造り地蔵尊で、赤あざを治してくれる地蔵尊と言うことで、赤身地蔵と言われている。旧暦の24日が縁日である。(彫刻)
木造十一面観世音菩薩(飯前観音)

飯前に所在し、治承年間、飯前の館主真家氏の祗願所として奉られたと伝えられている。高さ47.5cmの寄木造りの十一面観音像で安産の観音様として親しまれている。7月17日、10月18日が縁日である。(彫刻)
木造虚空蔵菩薩

荒地に所在し、泰永山修善院果雲寺の本尊として奉られている。高さ50cmの木造虚空蔵菩薩で、知恵と功徳を授けてくれる虚空蔵菩薩として親しまれている。(彫刻)
烈公書神名記

本間玄琢が小川に「稽医館」を開設した時、藩主徳川斉昭(烈公)が医学の神様二神の神名を直筆で記して「稽医館」に授けたものと伝えられている。(書画)